現代社会では、子どもたちの間でゲームが重要な娯楽やコミュニケーションツールとして広く普及しています。しかし、不登校の子どもにゲームを禁止するべきかどうか、親として悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、
✅ ゲームを禁止することのメリットとデメリット
✅ ゲームの中で成功体験を得やすい
✅ 親が取るべき具体的な対策
について詳しく解説します。
子どもの心情に寄り添い、適切なアプローチを模索することで、親子で新たな一歩を踏み出すヒントが見つかるはずです。ぜひご参考にしてみてください。
1. 不登校の子どもにゲームを禁止するのは正しい選択か?
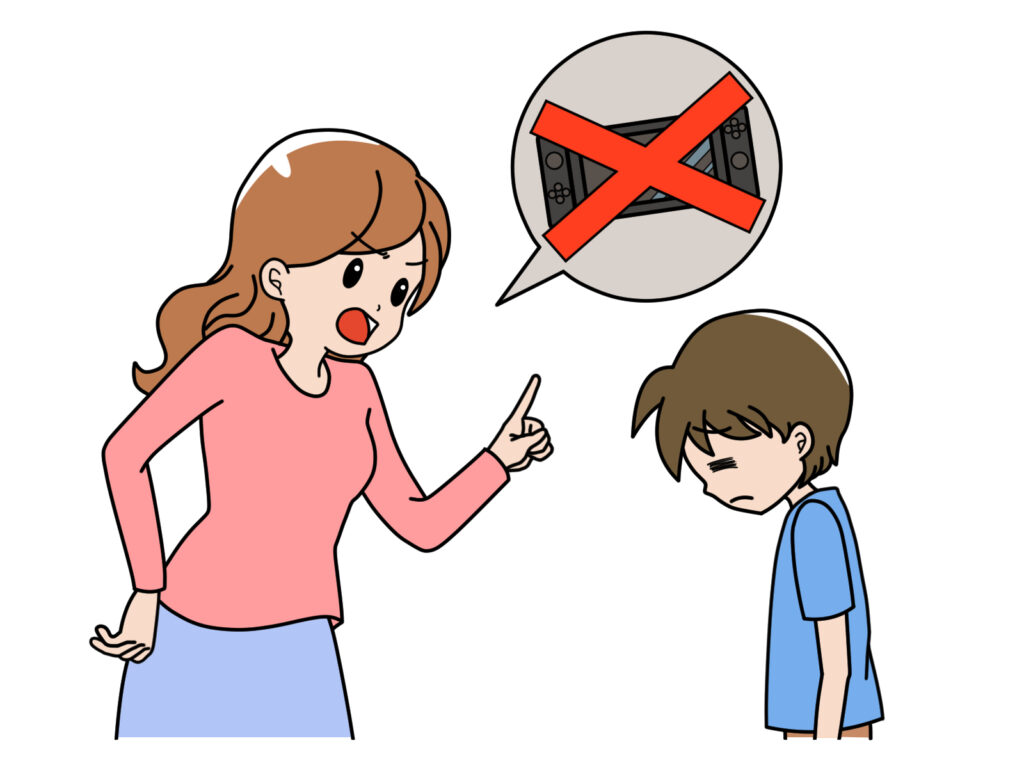
不登校の子どもに対する対応は、親や教育関係者にとって非常に繊細な問題です。その中で「ゲームを禁止する」という方法がよく検討されますが、果たしてそれは正しい選択なのでしょうか?
子どもたちにとって、ゲームは単なる娯楽にとどまらず、時にはストレスを発散する重要な手段となっている場合があります。特に不登校の子どもにとっては、学校という社会的な場を失った代わりに、ゲーム内でのコミュニケーションや自己表現が大きな支えとなることもあるのです。そのため、頭ごなしにゲームを禁止することが、彼らの心にどのような影響を及ぼすかを十分に考える必要があります。
一方で、ゲームが長時間にわたり生活の中心となってしまう場合、昼夜逆転や学業の遅れ、さらには依存症につながる可能性も否定できません。親としては、「ゲームを完全に禁止すべき」と考えるのではなく、適切なルールや制限を設けることが重要です。例えば、子どもと一緒にゲームの使用時間を話し合い、日々の生活リズムを守るためのガイドラインを作成することが考えられます。
「ゲーム禁止」という一方的な措置は、時に子どもの反発やストレスを増大させ、親子関係に亀裂を生じさせるリスクもあります。そのため、親は子どもの心情や背景に寄り添いながら、ゲームとの適切な関係を見つけることを目指すべきです。
結論として、不登校の子どもにゲームを禁止することが正しい選択かどうかは、単純な二択ではありません。それぞれの家庭や子どもの状況に応じて、柔軟に対応することが求められます。重要なのは、親子間の信頼関係を大切にしながら、子どもが前向きに日常を過ごせる環境を整えることです。
2. ゲーム禁止のメリット・デメリット

ゲーム禁止のメリット
ゲームを禁止することで得られるメリットとして、まず挙げられるのは 学業や生活習慣の改善 です。不登校の子どもの場合、昼夜逆転など不規則な生活が続きがちで、それが心身の健康や日常生活に悪影響を及ぼします。ゲームを禁止することで、こうした悪循環を断ち切り、生活リズムを整えるきっかけになる場合があります。また、ゲームに費やしていた時間を学習や他の活動に充てられるようになれば、子どもの知識やスキルの向上につながる可能性があります。
さらに、ゲーム依存症の予防 という観点でもゲーム禁止は一定の効果を発揮します。ゲームの過剰な利用は子どもの自己制御能力に悪影響を与え、場合によっては依存症へと発展するリスクがあります。このリスクを軽減し、健全な成長を促すために、ゲームの使用を一時的または完全に禁止する選択は理にかなっています。
また、ゲーム以外の趣味や興味を開拓する機会を提供することも、重要なメリットです。例えば、スポーツや読書、アートなど多様な活動に触れることで、子どもの視野が広がり、新しい世界に興味を持つ可能性が高まります。
ゲーム禁止のデメリット
一方で、ゲーム禁止にはいくつかのデメリットも存在します。特に、不登校の子どもにとってゲームは単なる娯楽以上のものであり、ストレス解消の手段 や 社会的つながりを保つ手段 となっている場合があります。ゲームを禁止することで、これらの利点を失う結果になり、子どもの精神的な負担を増大させる可能性があります。
また、禁止という形でルールを強制することで、親子間の信頼関係の崩壊 を招く恐れがあります。子どもは自身の楽しみを奪われたと感じ、親に対して反発や不信感を抱くことがあります。特に、不登校の子どもの場合、家庭内での信頼関係は重要な支えとなるため、その絆が弱まることは避けるべきです。
さらに、ゲームを禁止することで、子どもが現実から逃れるための手段を失い、自己否定感の強まりや無気力化 を引き起こす危険性もあります。この状態になると、子どもが学校や社会に戻るための意欲を失ってしまうことにもつながります。
3. 不登校の子どものゲーム禁止がもたらすリスクとは?

1)ゲームが唯一の気晴らしになっている場合、ストレスが爆発することも
不登校の子どもにとって、ゲームはただの娯楽ではなく、ストレスを解消するための重要な手段となることがあります。学校での人間関係や学習のプレッシャーから解放されるための一時的な逃げ場として、ゲームが機能している場合も多いです。このような状況でゲームを突然禁止すると、ストレスの発散場所を失い、精神的な負荷が一気に高まる可能性があります。その結果、感情がコントロールできなくなり、暴力的な行動や無気力状態に陥るリスクも考えられます。
2)強い反発や親への不信感が生まれる
子どもにとって、親からの「ゲーム禁止」の一方的な指示は、自分の意思や感情が尊重されていないと感じる原因となります。その結果として、親に対する反発心や不信感が生まれることがあります。このような感情の蓄積は、親子間のコミュニケーションをさらに難しくし、関係性の悪化を招きかねません。不登校という繊細な状況において、信頼関係を損なうことは、子どもの心のケアにおいて最も避けるべきリスクの一つです。
3)自己否定感が強まり、無気力になる可能性も
不登校の子どもは、すでに自己否定感や孤独感を抱えていることが少なくありません。ゲームを通じて感じていた小さな達成感や喜びが奪われると、自己否定感がさらに強まり、無力感や無気力感に繋がる危険があります。このような心理状態に陥ると、子どもは意欲を失い、再び学校や社会に戻るための第一歩を踏み出すエネルギーを見つけられなくなるかもしれません。
4)親子の信頼関係が崩れ、会話が減る
ゲーム禁止が親子関係に及ぼすもう一つの影響は、会話や関わりの減少です。ゲーム禁止を巡る対立が続くと、子どもは親との距離を取るようになり、家庭内でのコミュニケーションが減少します。特に不登校の子どもにとって、親子間の信頼関係は日常生活の重要な支えとなるため、この関係が損なわれることは大きなリスクです。子どもとの会話を大切にし、彼らの気持ちや考えを理解する努力が必要です。
5)ゲーム以外の楽しみを見つける機会を失うことも
ゲームを禁止することは、逆に子どもの選択肢を狭める結果になる場合もあります。新しい趣味や活動を見つけることをサポートする時間がないままゲームを禁止すると、子どもは他に楽しみや居場所を見つけられず、より孤立感を深める可能性があります。親はゲーム以外の選択肢を一緒に探す努力をすることで、子どもの可能性を広げ、より良い経験を積む手助けができます。
4. なぜ不登校の子どもはゲーム依存になりやすいのか?

1)ゲーム内のつながりで孤独感を埋められるから
不登校の子どもがゲーム依存になりやすい理由の一つは、ゲームが孤独感を埋める重要な手段となっていることです。学校という社会的な場を失った子どもたちにとって、オンラインゲームを通じて得られる仲間とのつながりは、大きな支えとなります。現実の世界で人間関係が希薄になる中、ゲーム内のフレンドやチームメンバーとの交流は、コミュニケーション不足を補う役割を果たします。このようなつながりが強化されることで、ゲームが一種の居場所として機能し、依存が生じるのです。
2)現実のストレスから逃れる手段になっているから
不登校という状況そのものが子どもにとって大きなストレス源となります。学校でのプレッシャーやいじめ、学業の負担から解放されるために、ゲームは心の逃げ場として利用されることがあります。ゲームの中では現実とは異なる世界観が広がっており、自分自身を投影するキャラクターを操作することで、ストレスを一時的に忘れることが可能です。このような「現実逃避」の手段として機能することで、ゲームへの依存が進むことがあります。
3)達成感を得やすく、自己肯定感が高まりやすいから
ゲームの特徴として、短時間で明確な達成感を得られる仕組みがあります。不登校の子どもは学校での評価や成果を得る機会が少ないため、ゲーム内での成功体験が自己肯定感を支える大きな要因となります。レベルアップやスコアの向上、難しいクエストのクリアなど、これらの達成感は現実世界での努力よりも即効性があり、手軽に得られるため、より強い依存心を生む要因となるのです。
4)昼夜逆転でゲーム中心の生活習慣になってしまっているから
不登校の子どもの場合、学校に通わないことで生活リズムが乱れがちです。特に夜遅くまでゲームをすることで昼夜逆転の生活に陥り、それが日常生活全般に影響を及ぼします。昼間は眠り、夜に活動するサイクルが固定化されると、ゲームが日常の中心となり、その中毒性から抜け出すことが難しくなります。このような生活習慣が依存を一層深刻化させる要因となっています。
5. もしゲーム依存になってしまったら?親ができる対策のポイント

1)頭ごなしに禁止せず、子どもの気持ちを理解する
ゲーム依存になってしまった場合、最も重要なのは子どもの気持ちを尊重し、理解する姿勢です。依存状態にある子どもは、現実から逃れるためにゲームを選択している場合が多く、その背景には孤独感やストレスが隠されています。「ダメだから禁止」という一方的なアプローチは、子どもの反発心を高めるだけでなく、親子関係に悪影響を及ぼすことがあります。まずは子どもがどのような状況でゲームを使用しているのか、その理由や感情をじっくりと話し合い、共感することが第一歩となります。
2)「いきなり禁止」ではなく、無理のない範囲で時間を調整する
ゲーム依存の克服には、いきなり完全禁止を実行するのではなく、徐々に使用時間を減らす方法が有効です。例えば、「1日2時間まで」といった具体的なルールを設けることで、子どもが無理なく適応できる環境を作ります。また、このルールを決める際には、子どもと一緒に話し合いながら決定することが重要です。自主的に取り組む姿勢を促すことで、依存克服へのモチベーションを高めることができます。
3)ゲーム以外の楽しみや居場所を見つけるサポートをする
ゲーム依存から抜け出すためには、ゲームに代わる楽しみや居場所を見つけることが鍵となります。スポーツやアート、読書、地域活動など、子どもの興味を引き出すような活動を一緒に探す努力をすることが大切です。また、子ども自身が新しい活動に挑戦するきっかけを作るために、親は積極的に環境を整える役割を果たすべきです。ゲーム以外の世界にも価値があることを知ることで、依存からの脱却をスムーズに進めることができます。
4)生活リズムを整え、学習の習慣を取り戻す
ゲーム依存によって乱れてしまった生活リズムを回復することは、依存克服における重要なステップです。具体的には、寝る時間や起きる時間を固定し、日常生活のペースを整えることから始めます。その上で、学習習慣を少しずつ取り戻す努力をすることで、学校や社会に戻る準備が進みます。親は子どもが自分のペースで取り組める環境を提供し、過度なプレッシャーをかけないように注意しましょう。
5)必要に応じて専門機関やサポートサービスを活用する
ゲーム依存が深刻化している場合には、専門機関やサポートサービスの活用も視野に入れるべきです。心理カウンセリングや依存症治療の専門家は、子ども自身だけでなく、親の悩みや質問にも対応してくれます。適切な支援を受けることで、依存克服のプロセスがより効率的に進む可能性があります。また、親自身も情報収集を行い、最新の知識を活用して対応策を練ることが重要です。
6. 不登校になりやすい家庭の特徴とは?
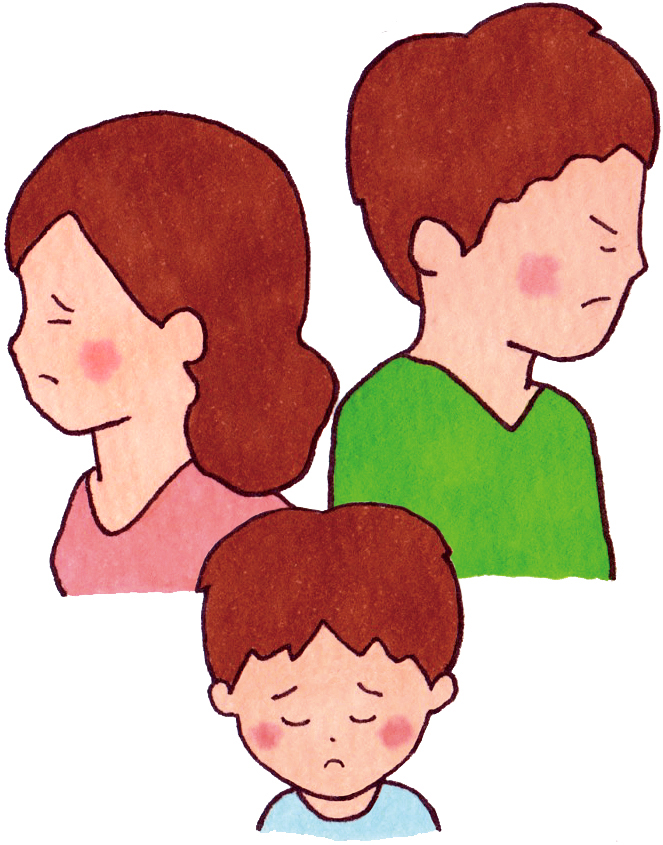
1)過度なプレッシャーや厳しいルールがある
家庭内での過度なプレッシャーや厳しいルールは、不登校につながりやすい要因の一つです。たとえば、成績や進学に対する過剰な期待、日常生活において細かすぎる規則を設けることなどが子どもの心理的負担を増大させます。これにより、子どもは「家では休まることができない」という感覚を持ち、学校という別のプレッシャーの場から逃避しようとするケースがあります。親が子どもの個性や成長スピードを尊重しない場合、この状況はさらに悪化する可能性があります。
2)親子の会話が少なく、気持ちを共有しづらい
親子間のコミュニケーションが少ない家庭も、不登校につながる要因となることがあります。親子の会話が減少すると、子どもが自分の悩みや感情を共有する機会が減り、孤立感を感じることがあります。また、子どもの考えや気持ちを理解する努力がなされない場合、子どもは家庭内で安心感を得られなくなり、その結果として学校に行くことに対する意欲を失うことがあります。親子間の対話は、子どもが自分を肯定し、外の世界に向き合う力を持つための重要な要素です。
3)過干渉または無関心な育て方になっている
家庭内での親の関与が「過干渉」または「無関心」に偏る場合、子どもは不登校になりやすい傾向があります。過干渉では、親が子どもの行動を過度に管理し、自立心や自己決定力を阻害します。反対に、無関心な育て方では、子どもが愛情や支えを感じることができず、心の孤立を深めてしまいます。適切な関わり方を見つけることが、子どもの健全な成長を促す鍵となります。
4)親同士の不仲や叱責が多く家庭内の雰囲気がピリピリしている
親同士の不仲や頻繁な叱責が行われる家庭環境も、不登校の要因となり得ます。家庭内の雰囲気が常にピリピリしていると、子どもは安心して過ごすことができません。特に、親の間で対立が絶えない場合、子どもはそのストレスを感じ取り、心の安定を失ってしまうことがあります。家庭は子どもにとっての「安全な場」であるべきですが、この役割が果たされない場合、学校に行くことへの意欲が薄れる可能性があります。
5)子どもの自己肯定感を育む機会が少ない
家庭で子どもの自己肯定感を育む努力が欠けている場合も、不登校につながるリスクが高まります。子どもは日常生活や学校生活で何かを達成した際に、親からの承認や励ましを得ることで、自分を肯定的に捉える力を育みます。しかし、その機会が少ない場合、子どもは「自分には価値がない」と感じることが増え、学校という場でさらなる否定的な経験を避けようとする可能性があります。
7.まとめ
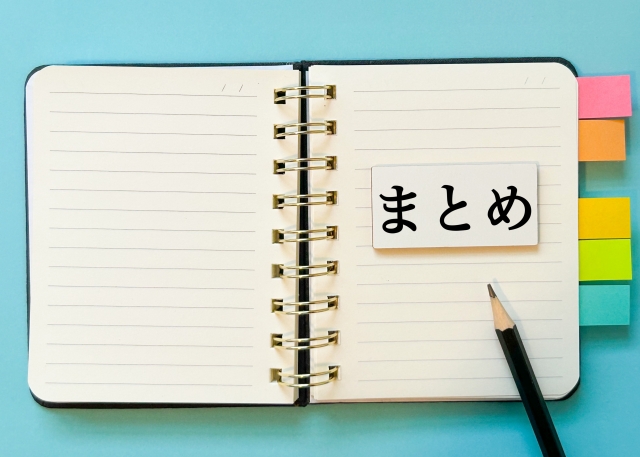
不登校の子どもに対するゲーム禁止という対応策は、単純な解決方法ではありません。これまでの記事を通じて、不登校の子どもがゲームに依存する背景や、ゲーム禁止がもたらすリスク、そして親が取るべき適切な対応について多角的に考察してきました。これを踏まえ、最も重要なのは、子どもの気持ちや状況に寄り添いながら問題解決を目指すことです。
不登校の子どもが抱える孤独感やストレスは、ゲームを通じて一時的に解消されている場合があります。そのため、親が子どもを一方的に制限するのではなく、ゲーム以外の楽しみや居場所を見つける努力をすることが重要です。新しい活動や趣味を探す手助けを通じて、子どもが現実世界で自分の価値を見出す経験を増やしていくことができます。
また、親子の信頼関係を維持することも不可欠です。ゲーム禁止が子どもの強い反発や親への不信感を招くことがあるため、禁止の代わりにルールの設定や時間管理を話し合いながら進めることが効果的です。このプロセスを通じて、子どもは自分の意見や意思を尊重される感覚を持ち、依存克服への意欲を高めることができます。
そのためにはゲーム以外の楽しみを見つけるサポートが解決への第一歩となります。
最終的に不登校を克服するためには学習習慣を取り戻すことも重要となってきます。勉強への前向きな気持ちが芽生えた時に子どもが安心して取り組める環境づくりも準備しておきましょう。学習習慣を取り戻すには、モチベーションの維持が不可欠です。そのためには適切な目標設定、学習スケジュールの作成と進捗管理が必要です。最初から子供に任せるのは負荷がかかり過ぎて失敗につながりやすく、親が介入すると適切な目標設定ができない恐れもありますので、コーチング付きの教材が有効です。そこでおすすめなのは「e-学び」です。自宅学習に必要な機能や特性を兼ね備え、どの学年からでも無理なく進められる教材となっています。専属コーチによるヒアリングや学習計画作成、こまめな学習状況のフィードバックなどの手厚いサポートが受けられます。親子と専属コーチとの連携で継続率も向上しています。ゲーム依存を改善して学習習慣を身に着けるために一歩ずつ進んでいきましょう。
初めての方でも安心してご利用いただける無料体験プログラムをご用意していますので、この機会に、お子さまに合った学習スタイルを見つけてみませんか?
無料体験のお申し込みはこちらからどうぞ!
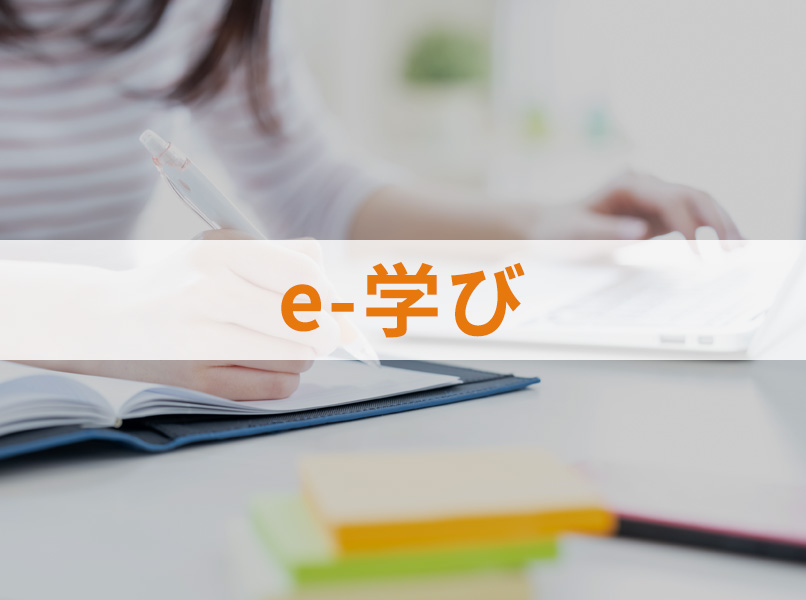
不登校やゲーム依存、学習の遅れに悩むお子さまと保護者の方を支援するオンライン学習サービス「e-学び」の講師。長年、地域の大手学習塾にて個別指導に携わり、様々な背景をもつ生徒と向き合ってきました。不登校やゲーム依存のご相談は随時受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。




