「不登校になってから、子どもがゲームばかり…。このままじゃゲーム依存になってしまうのでは?」不登校のお子さんを持つ親御さんの中には、このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
実際に、不登校の子どもは ゲーム依存になりやすい と言われています。その背景には、
✅ 現実世界のストレスから逃れられる
✅ ゲームの中で成功体験を得やすい
✅ 友達とオンラインでつながれる
といった理由があります。しかし、 「ゲームをやめさせるべき!」と頭ごなしに否定すると、かえって逆効果になることも…。
では、不登校の子どものゲーム依存を防ぎながら、勉強や日常生活に戻れるようにするにはどうすればよいのでしょうか?
この記事では、
- 不登校の子どもがゲーム依存になりやすい理由
- ゲームをやめさせるのではなく「適切に付き合う」方法
- ゲーム依存を改善しながら学習習慣を身につけるコツ
- 親としてできるサポート方法
を詳しく解説します。
同じような悩みをお持ちの方は是非参考にしてみてください。
1. 不登校の子どもがゲームに依存してしまう原因とは?

1)ゲーム以外にすることが見つからないから
不登校の子どもがゲームに依存してしまう主な理由の一つは、ゲーム以外の活動が見つからない状況に置かれているからです。不登校になると、学校での活動や友人との交流がなくなり、家庭内で過ごす時間が多くなります。このような状況では、自分を没頭させられる活動を探すことが難しくなり、手軽で刺激的なゲームに頼りがちです。
さらに、不登校の子どもは、学校での勉強やクラブ活動の代わりとなる新しい趣味や興味を見つける機会が減少します。親や周囲の人々がその子の興味に寄り添い、多様な選択肢を提供することが重要です。例えば、スポーツや音楽、アートなど、子どもが楽しめる可能性のある活動に触れる機会を増やすことで、ゲーム以外の充実感を味わえる場が生まれるかもしれません。
ゲーム以外の魅力的な活動を見つけることで、不登校の子どもがゲーム依存から抜け出し、健全な日常生活を取り戻す第一歩となります。活動の選択は子どもの個性に合わせ、焦らず進めることが大切です。
2) ゲームの世界に没頭すると現実を忘れられるから
不登校の子どもがゲームに依存する理由の一つとして、ゲームの世界に没頭することで現実を忘れられる点が挙げられます。現実の中で不安やストレスを感じている子どもにとって、ゲームはそれらの問題を一時的に回避できる避難所となり得ます。特に不登校という状況では、学校生活や人間関係からのプレッシャーが強く、現実から距離を置く手段としてゲームを選びやすいのです。
ゲームの中では、プレイヤーが思い通りに動かせるキャラクターや分かりやすいルールが存在します。これにより、子どもは達成感や充実感を得やすく、現実の複雑さや困難さを一時的に忘れることができます。また、ゲームの中で活躍することで自己肯定感が高まり、それがさらにゲーム依存を助長する要因にもなります。
しかし、ゲームによる現実逃避が続くと、家庭内や社会とのつながりが薄れる可能性もあります。親や周囲がまずは子どもの気持ちを理解し、何にストレスを感じているのかを話し合うことが重要です。対話を通じて、現実の世界でも安心感を持てる環境を少しずつ整えることが、ゲーム依存を改善する鍵となるでしょう。
3) 純粋にゲームを楽しんでいるから
不登校の子どもがゲームに依存してしまう原因の一つとして、純粋にゲームを楽しんでいることが挙げられます。ゲームはその魅力的なストーリーや刺激的なプレイ体験を通じて、子どもたちに大きな楽しさを提供します。特に、不登校によって日常生活が単調になりがちな子どもにとって、ゲームは非日常の世界で冒険できる貴重な手段となります。
また、ゲームをプレイすることで得られる達成感や喜びは、現実世界での成功体験に代わるものとして機能します。レベルを上げたり、難しいクエストをクリアしたりすることで、自分の努力が報われるという感覚を得られるのです。このような感覚は、不登校の子どもにとって自己肯定感を高める貴重な機会となることもあります。
しかし、ゲームの楽しさがきっかけでプレイ時間が長くなりすぎる場合、生活リズムの乱れや他の活動の時間が奪われることもあります。そのため、子どもがゲームを楽しむ中でも、家族や周囲が適切なバランスを支援することが重要です。ゲームそのものの魅力を理解しつつ、他の楽しみや目標も提案することで、子どもが多様な経験を得られる環境を整えていきましょう。
4) ゲームの中に自分の居場所があるから
不登校の子どもがゲームに依存する理由の一つとして、ゲームの中に自分の居場所を見つけている点が挙げられます。現実世界では学校や家庭で孤立感を抱えている場合、ゲームの世界では仲間や共通の目的を持つ人々と交流することができ、自分が受け入れられる場所を感じられることがあります。特にオンラインゲームでは、プレイヤー同士のコミュニケーションが活発に行われるため、現実よりも居心地の良い空間として作用することが多いです。
ゲーム内での成功体験や他者との協力は、不登校の子どもにとって大きな自己肯定感を生む要因となります。キャラクターを成長させたり、難しいミッションを仲間とクリアすることで、「自分にも価値がある」と感じることができるのです。このような経験は、現実世界で得られない承認や達成感を補完する役割を果たしています。
しかし、ゲームの中で居場所を感じることが悪いわけではありませんが、それに依存しすぎると現実世界での居場所作りが困難になる可能性があります。親や周囲の大人は、ゲーム内で感じる「居場所」の利点を理解すると同時に、子どもが現実世界でも安心して過ごせる環境を少しずつ構築する努力をすることが重要です。子どもに寄り添いながら、ゲーム以外のコミュニティや活動の場を提案することで、ゲームとのバランスを見つける手助けができます。
5) ゲームをクリアすると達成感が得られるから
不登校の子どもがゲームに依存してしまう理由の一つとして、ゲームをクリアすることで得られる達成感の存在が挙げられます。ゲームは明確な目標を提示し、適切な努力を積み重ねればその目標を達成できる仕組みになっています。これにより、達成感や自己効力感が得られやすいのです。不登校という状況下では、学業や社会生活で得られる達成感が欠けている場合が多く、ゲームの中での成功体験が心の安定につながることがあります。
また、ゲームのクリア時に得られる報酬や演出はプレイヤーに強い満足感を与えます。子どもは現実世界の複雑な問題を忘れ、ゲーム内での達成感に満たされることで、自分自身の価値や存在意義を再認識することができます。このようなポジティブな体験が繰り返されることで、ゲームが生活の中心となり、依存状態に陥る可能性もあります。
2.不登校の子どものゲーム依存の影響

この場合、親や周囲の大人は、ゲーム内で得られる達成感の良い面を理解しつつ、現実世界でも達成感を得られる仕組みを少しずつ作ることが重要です。例えば、学習の目標や家庭内での役割などを設定し、小さな成功体験を積み重ねることで、子どもの自信を取り戻す手助けができます。子どもがバランスよく日常生活を送れるようにサポートすることで、ゲーム依存の解消につなげることができるでしょう。
不登校の子どもがゲーム依存に陥ることで、生活の様々な側面に深刻な影響を及ぼすことがあります。ゲーム依存が引き起こす主な問題は、身体的、心理的、そして社会的な側面にまたがります。以下では、その影響を具体的に見ていきます。
1)昼夜逆転し生活リズムが崩れる
不登校の子どもがゲーム依存になると、昼夜逆転が起こりやすくなります。夜遅くまでゲームをプレイすることで、朝起きる時間が遅くなり、生活リズムが乱れることがよくあります。このような状況が続くと、体調不良や集中力の低下を招き、健康面への悪影響が懸念されます。さらに、不規則な生活によって不安やイライラ感が増幅され、精神的な負担が蓄積する可能性があります。
2)家庭内のコミュニケーションが不足する
ゲーム依存により、子どもが家庭内での交流を避けるようになるケースも少なくありません。ゲームに夢中になることで、親や兄弟との会話が減り、家庭内での孤立感が強まることがあります。このような状況では、親子間の信頼関係が希薄になり、子どもが自分の悩みや感情を共有しづらくなる可能性があります。また、家族全体の絆が弱まり、家庭内の問題解決能力に影響を及ぼすこともあります。
3)勉強する習慣がなくなり将来に影響が出る
ゲーム依存が進むと、学習意欲が低下し、勉強する習慣が失われることがあります。不登校の子どもは学校で学ぶ機会を失っている状況で、さらに自宅での学習時間がゲームに費やされると、学力の低下は避けられません。この結果、進学や就職の選択肢が狭まる可能性があり、将来的なキャリアや自己実現の機会を制限してしまう危険性があります。さらに、学びから得られる達成感や知的な刺激を失うことで、精神的な充実感を得ることが難しくなる場合もあります。
3.不登校の子どもがゲーム依存になってしまった際の対処法

不登校の子どもがゲーム依存に陥ってしまった場合、その状況を改善するためには、子どもの気持ちに寄り添い、根本的な原因を考慮した適切な対処法を実践することが必要です。以下では、具体的な対処法を詳しく解説します。
方法① 遊ぶ時間を決めて、メリハリをつける
ゲーム依存を改善するための第一歩として、明確なルールを設け、遊ぶ時間を制限することが重要です。例えば、「1日2時間まで」「夕食後のみ」といった具体的な時間を設定することで、子ども自身がゲーム時間を管理する習慣を身につける手助けができます。ただし、この際に無理やり時間を取り上げるのではなく、子どもと話し合いながら合意を形成することがポイントです。子どもが納得する形でルールを設けることで、親子関係の信頼を損なわずに依存改善へとつなげることができます。
方法② 1日の流れを決めて規則正しく過ごす
不登校の子どもは、学校に通わないことで生活リズムが崩れやすい傾向があります。規則正しい生活リズムを取り戻すためには、1日のスケジュールを具体的に決めることが効果的です。例えば、朝は同じ時間に起床し、昼食や休憩の時間も計画的に設定することで、ゲーム以外の時間が増える環境を作ることができます。このような生活リズムを整えることで、心身の健康が改善され、ゲームへの依存度が自然と低下する可能性があります。
方法③ 生活の中に小さな目標を作る
子どもがゲームに依存する背景には、現実の中で目標を見失っているという要因があります。そのため、日常生活の中に達成可能な小さな目標を作ることが有効です。例えば、「毎日10分本を読む」「夕食の後片付けを手伝う」といった目標を設定し、それを達成した際には適切に褒めることで、子どもの自己肯定感を高めることができます。このようなプロセスを通じて、ゲーム以外でも達成感を得られる経験を増やすことができます。
方法④ ゲーム以外に熱中できるものを見つける
ゲーム依存を改善するためには、ゲーム以外に興味を持てる活動を提案することが大切です。例えば、スポーツ、音楽、絵画、プログラミングなど、子どもの興味や才能に合った活動を一緒に探すことが効果的です。親が積極的にサポートし、共に取り組むことで、子どもは新しい楽しみを見つけやすくなります。また、外部のクラブや教室に参加することで、社会とのつながりも取り戻すことが期待できます。
方法⑤ 家の外にも安心できる場所を作る
不登校の子どもにとって、家以外の「安心できる場所」を見つけることは非常に重要です。例えば、地域のフリースクールや図書館、児童館など、気軽に足を運べる場所を紹介することで、子どもの視野を広げる手助けができます。また、これらの場所で新しい友人やメンターとの出会いがあることで、ゲーム以外での交流が活発になり、依存の改善に寄与します。
方法⑥ 親もゲームに関心を持ち、会話のきっかけにする
ゲーム依存を解消するためには、親がゲームに対して否定的な姿勢を取るのではなく、子どもがどのようなゲームをプレイしているのか関心を持つことも大切です。例えば、親自身が一緒にゲームをプレイし、その中での話題を共有することで、親子間の会話が増えます。このようなコミュニケーションを通じて、ゲームの良い面と悪い面を冷静に話し合うことが可能になります。
方法⑦ 学習とゲームをバランスよく取り入れる
学習とゲームのバランスを取ることも、重要な対処法の一つです。例えば、「1時間勉強したら30分ゲームをして良い」といったルールを設けることで、学習習慣とゲーム時間を調整することが可能です。また、ゲーム自体を学習に活用する方法も検討できます。教育的なゲームやプログラミング関連のゲームは、学びと楽しさを両立させる有効な手段となります。
4. ゲーム依存の不登校の子を持つ親が気をつけるべきこと
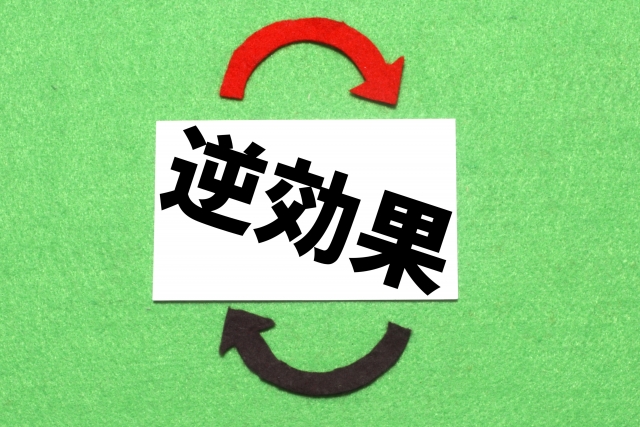
不登校の子どもがゲーム依存に陥ったとき、親としてどのように接すれば良いのか迷うこともあるでしょう。しかし、冷静に状況を受け止め、適切な対処を取ることが、子どもの将来にとって非常に重要です。ここでは、ゲーム依存の子どもを持つ親が注意すべきポイントについて詳しく解説します。
注意点① 無理やりゲームを取り上げるのは逆効果
ゲームを禁止したり、無理に取り上げたりする行為は、子どもの反発を招き逆効果になることが多いです。子どもにとってゲームは、現実逃避や自己表現の手段であることを理解し、ゲームに対する考え方を共有することが重要です。ゲームのプレイを徐々に減らすような柔軟なアプローチを取りましょう。
注意点② 感情的に怒らず冷静に向き合う
親が感情的になり過ぎると、子どもとのコミュニケーションが断絶してしまう可能性があります。冷静に子どもの気持ちや状況を聞き取ることで、問題解決の糸口を見つけることができます。例えば、「なぜゲームが好きなのか」や「他に何がしたいのか」を穏やかに尋ねてみましょう。
注意点③ ゲームの良い面にも目を向ける
ゲームを一概に否定するのではなく、その良い面にも目を向けることが大切です。例えば、ゲームを通じて得られる達成感や問題解決能力、友人との交流は、子どもの成長に役立つ要素です。こうした点を認めつつ、ゲームとのバランスを取る方法を一緒に考えることが効果的です。
注意点④ 課金トラブルやネット犯罪に注意する
オンラインゲームでは、課金やネット上のトラブルが問題となることがあります。親は子どもと一緒にゲームの安全性を確認し、課金のルールを設定することが重要です。また、ネット犯罪に巻き込まれないよう、子どもがどのような人と交流しているのかを把握しておくことも大切です。
注意点⑤ ゲーム依存が疑われる場合は専門家に相談する
家庭内での対応が難しいと感じた場合は、専門家に相談することも選択肢の一つです。カウンセラーや児童心理士と連携することで、問題の根本原因にアプローチし、子どもにとってより良い環境を整えることが可能になります。
注意点⑥ 子どもの気持ちを理解し、信頼関係を築く
親子間の信頼関係を構築することは、ゲーム依存からの脱却に向けた最も重要な要素です。子どもの気持ちや悩みを理解し、共感することで、問題解決のためのパートナーシップを築くことができます。
注意点⑦ ゲーム以外のコミュニティや学習の機会を提供する
子どもがゲーム以外の活動に興味を持てるよう、コミュニティや学習の場を提供することも効果的です。例えば、地域のフリースクールやスポーツクラブ、オンライン学習プログラムなど、多様な選択肢を用意してみましょう。
5.まとめ

不登校の子どものゲーム依存を解消するために、まずは生活のリズムを整えることが大切です。そのためには具体的な1日のスケジュールを決め、小さな目標を作り、達成する経験や褒められる喜びを繰り返すことで、子どもの自己肯定感を育むことができます。また親子のコミュニケーションを深める事も重要なポイントです。親との信頼関係が深まることで親からの前向きな働きかけは、子どもの学習意欲を引き出し、ヤル気の向上につながります。ゲームを禁止するのではなく勉強とバランス良く両立できるように、時間を決めて取り組む事や達成感を感じやすくゲーム感覚で取り組める教材や学習方法の工夫を検討してみるのも良いと思います。そこでおすすめなのは「e-学び」です。子どもが無理なくステップアップできるよう工夫されています。またゲーム感覚で学べる教材で飽きやすい子どもにもおすすめです。専属コーチによるヒアリング・学習計画・進捗報告などが手厚く、親子と専属コーチとの連携で継続率も向上しています。ゲーム依存を改善して学習習慣を身に着けるために一歩ずつ進んでいきましょう。
初めての方でも安心してご利用いただける無料体験プログラムをご用意していますので、この機会に、お子さまに合った学習スタイルを見つけてみませんか?
無料体験のお申し込みはこちらからどうぞ!
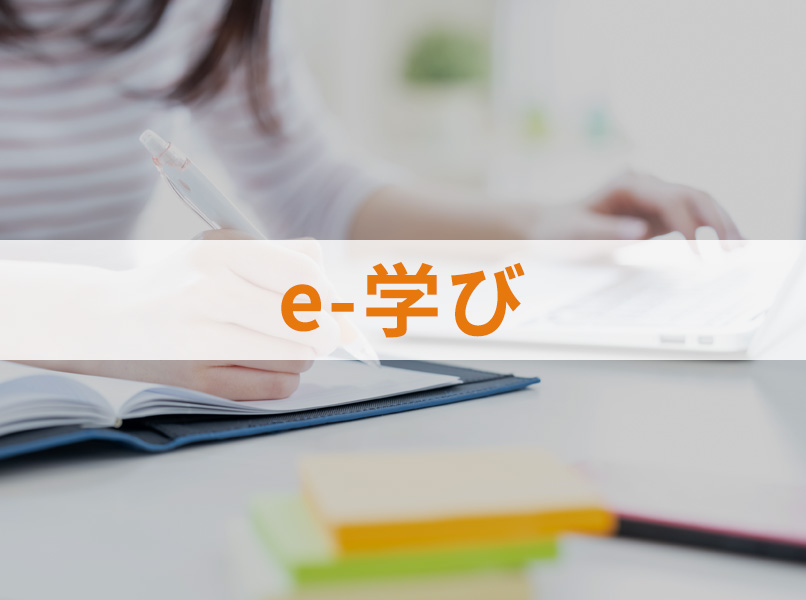
不登校やゲーム依存、学習の遅れに悩むお子さまと保護者の方を支援するオンライン学習サービス「e-学び」の講師。長年、地域の大手学習塾にて個別指導に携わり、様々な背景をもつ生徒と向き合ってきました。不登校やゲーム依存のご相談は随時受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。




