「うちの子、不登校になってから勉強しなくなって、ゲームばかり…。どうしたらいいんだろう?」
このような悩みを抱えている親御さんは多いのではないでしょうか?
不登校の子どもがゲームに夢中になる背景には、達成感を得やすい、現実逃避の手段になっているなど、さまざまな要因があります。単に「ゲームばかりしないで勉強しなさい!」と注意するだけでは、逆効果になることも…。大切なのは、子どもの気持ちを理解しながら、学習習慣を無理なく身につけられる環境を整えることです。
この記事では、
✅ なぜ不登校の子は勉強せずにゲームばかりするのか?
✅ 「勉強しなさい!」が逆効果になる理由
✅ ゲーム依存を改善しながら学習習慣をつける方法
✅ 親としてできるサポートの仕方
といった内容を詳しく解説していきます。
「うちの子も、少しずつ勉強に向き合ってくれるようになった!」と思える日が来るよう、一緒にできることから始めていきましょう。
不登校の子が勉強しないでゲームばかりするのはなぜ?

不登校の子供が勉強から遠ざかり、ゲームに夢中になる背景には、多くの要因が複雑に絡み合っています。それぞれの理由に注目し、親や周囲の理解を深めることで、より適切なサポートが可能です。
ゲームの方が「できる!」という達成感を得やすい
ゲームは短時間で目に見える成果を実感できる仕組みがあります。レベルアップやスコアの向上といった成功体験は、自信を失った子供にとって大きな喜びです。一方、勉強は成果がすぐには見えづらく、達成感を得にくいため、ゲームがより魅力的に感じられるのです。
勉強はつまらないと感じ、興味が持てない
興味を持てない内容に取り組むことは、誰にとっても苦痛です。教材や授業内容が子供自身の好奇心や日常生活と結びついていない場合、ゲームのような直感的で楽しいアクティビティに惹かれるのは自然なことです。
自信をなくし、学習意欲が低下している
過去の失敗や挫折から、「どうせ自分にはできない」と思い込む子供もいます。勉強を避け、自己肯定感が得やすいゲームに没頭するケースが多いです。小さな成功体験を積み重ねることが重要です。
現実逃避できるから
ゲームのストーリーや世界観は、子供に現実を一時的に忘れさせてくれます。不登校の子供にとって、ゲームは不安やストレスから逃れられる場所になっていることも多いです。
不登校の子に「勉強しなさい!」は逆効果?ゲームを禁止するリスク

不登校の子供がゲームに没頭していると、「勉強しなさい!」と、つい言いたくなるのは自然なことです。しかし、このアプローチは逆効果になり、かえって子供の心を閉ざしてしまう可能性があります。また、ゲームの使用を完全に禁止することもリスクを伴います。親としての気持ちは理解できますが、ここでは慎重に対処する必要があります。
ゲームを制限すると親子関係が悪化する
ゲームの制限は、自由を奪われる感覚になりやすく、親に対する反発心が芽生えることがあります。
我慢を強いられることで、ゲーム依存が悪化する可能性も
ゲームを禁止されると、逆にその魅力に強く惹かれることがあります。許可された瞬間に長時間プレイしてしまうリスクがあります。
自分で時間を管理する力が育たなくなる
ゲームを完全に禁止すると、子供が自分で時間を管理する力を養う機会を失うことがあります。適度なプレイを認めつつ、子供自身にルール作りに参加させることが重要です。
ゲーム依存を改善するために気を付けるべきこと

ゲーム依存が子供の生活や成長に影響を与えることは、親にとって大きな悩みの種です。しかし、ゲームを完全に禁止するのではなく、改善に向けて具体的な取り組みを進めることが重要です。以下では、子供が健康的な生活を取り戻すための具体的な方法を掘り下げて解説します。
生活リズムを整え、計画的に過ごす
夜更かしや朝寝坊を防ぎ、規則正しい生活を送ることで心身の健康を改善します。ゲーム以外の活動もスケジュールに組み込むことが大切です。
ゲームに振り回されないルール作り
家族で話し合い、一日あたりのプレイ時間を制限するなどルールを設定します。子供自身の意見を取り入れることで納得感を高めることができます。
ゲーム以外の楽しみを見つける工夫
ゲーム依存を解消するためには、ゲームに代わる楽しみを見つけることも欠かせません。例えば、スポーツ、音楽、アート、読書など、子供が興味を持ちやすい活動を一緒に探してみましょう。また、体験型のイベントや地域の活動に参加することで、ゲーム以外の世界の楽しさを実感できる場を提供することも効果的です。
親子で一緒にできる活動を増やす
親子間のコミュニケーションを深めることも、ゲーム依存改善の鍵となります。一緒に料理をしたり、散歩をしたりすることで、家族間のつながりを再確認できます。こうした活動を通じて、子供がゲーム以外の時間にも充実感を持てるよう支援しましょう。
頑張りを認め、前向きな働きかけをする
子供の小さな成功を見逃さず、その頑張りを褒めることが重要です。例えば、ゲームの時間を減らすことができたら、それをしっかりと評価し、次のステップへの意欲を引き出します。親の前向きな働きかけは、子供にとって大きな励みとなり、自信を持つきっかけになります。
勉強しないゲーム依存の不登校の子供が勉強するようになるための工夫4選

不登校でゲーム依存が進行している子供が、再び学びの場に向き合うようになるためには、一方的な制約ではなく、楽しさや達成感を通じて勉強への興味を引き出す工夫が必要です。以下では、子供の特性や状況に合わせた4つの具体的な工夫をご紹介します。
小さな目標を決め、達成感を積み重ねる
勉強に対する大きな抵抗感を持つ子供に対しては、初めから高い目標を設定するのではなく、達成可能な小さな目標を設定することが有効です。例えば、「10分だけ問題を解く」「1日1ページ読む」といった短時間でも達成可能なタスクを提示することで、子供に小さな成功体験を積み重ねさせます。この成功体験が自信となり、次第に大きな目標にも挑戦する意欲が生まれます。
勉強の楽しさを見つける
「楽しい!」と感じられる瞬間を提供することで、勉強に対する興味を引き出すことができます。そのためには、以下のような工夫が考えられます。
- 好きな分野から学び始める 子供が興味を持つテーマやトピックを見つけ、その分野に関連する教材や情報を活用しましょう。例えば、ゲームが好きな子供であれば、ゲームデザインやプログラミングに関する学習から始めるのも一つの方法です。
- ゲーム感覚で楽しめる教材を活用 学習アプリやオンライン教材を活用し、子供がゲーム感覚で勉強を楽しめる環境を整えます。スコアやレベルアップといった要素が盛り込まれた教材は、ゲームに似た達成感を提供し、学びへのモチベーションを高めます。
- 体験型の学習を取り入れる 博物館や科学館など、実際に体験を通じて学べる機会を提供することで、教科書では得られない興味や理解を引き出します。フィールドワークや実験なども、勉強が「楽しいもの」であると感じさせるきっかけになります。
- 実生活と結びつけた学びを意識する 例えば、料理を通じて計量や栄養素の勉強をするなど、日常生活の中に学びを取り入れることも効果的です。こうした工夫によって、勉強が自分の生活や興味に深く関わるものであることを実感させましょう。
親も一緒に学び、サポートする姿勢を見せる
子供が孤独に勉強するのではなく、親も一緒に取り組むことで、学びへの安心感を提供します。例えば、一緒に本を読む、一緒に課題に取り組むなど、親子の協力を通じて「勉強は楽しい活動だ」というイメージを形成することができます。また、親が自ら学ぶ姿勢を見せることで、子供にとっての良い手本となるでしょう。
勉強に集中できる環境を整え、ゲームとのバランスを取る
ゲーム依存が問題となる場合、勉強と遊びの時間を適切に管理することが大切です。例えば、勉強の時間とゲームの時間をスケジュール化し、子供と一緒に計画を立てることで、無理のないルールを作ります。
また、勉強の時間中はスマホやゲーム機を一時的に視界から遠ざける環境を整えることで、集中しやすくなります。一方で、完全な禁止を避けることも重要です。適度な息抜きを認めることで、子供のストレスを軽減し、勉強と遊びのバランスを保つことが可能です。
不登校の我が子が「勉強しない」と悩む親ができること

不登校の子供が「勉強しない」という悩みは、多くの親が抱える切実な問題です。しかし、強制的に勉強をさせるのではなく、子供に寄り添いながら学びへの意欲を取り戻すためのサポートが求められます。以下では、親としてできる具体的な取り組みについてご紹介します。
ゲームを完全に禁止せず、対話を大切にする
ゲームを禁止し、勉強を強要することは、一見効果的に思えるかもしれませんが、実際には逆効果になることが多いです。ゲームは子供にとってリラックスや達成感を得られる重要な活動であり、それを取り上げると、反発やストレスを招く可能性があります。むしろ、ゲームについて子供と対話し、どのように楽しんでいるのか、何が好きなのかを聞くことで、親子の絆を深めるきっかけにすることができます。また、ゲームの時間を適切に管理するルールを子供と一緒に作り、彼らが納得感を持てるよう配慮することが重要です。
勉強の楽しさを伝え、小さな成功体験を積ませる
勉強が「つらい」「退屈」と感じられている場合は、まずはその印象を変えることが必要です。子供が興味を持ちやすい分野やテーマから学びを始め、成功体験を積み重ねることで、自信と意欲が芽生えます。たとえば、好きなアニメやゲームに関連するトピックを取り上げることや、クイズ形式で学べる教材を活用するのも良いアイデアです。また、達成した成果をしっかりと認め、子供が「自分はできる」という実感を持てるよう支援しましょう。
無理なく続けられる学習環境を整える
勉強に集中できる環境を整えることも、親ができる大切なサポートです。静かで快適な空間を提供するだけでなく、子供の個性や好みに合った学習スタイルを尊重することも必要です。たとえば、長時間の集中が難しい場合は、短時間で取り組めるタスクに分けるなど、柔軟な方法を取り入れましょう。また、子供が「やらされている」と感じるのではなく、「自分で選んで取り組んでいる」と実感できる環境作りを目指します。
親自身も前向きな姿勢を持ち、安心感を与える
親が焦りや不安を抱えたまま子供に接する場合、その気持ちは子供にも伝わりやすくなります。親自身が前向きな姿勢を持ち、子供にとっての安心感を与えることが大切です。子供の成長を長期的に見守る姿勢を持ちながら、小さな進歩を喜び、共に歩む姿勢を示すことで、子供は自分に対する期待を感じ、自ら前に進む力を得ることができます。
まとめ

不登校でゲームばかりになりがちな子どもには、生活リズムを整えたり、ゲーム以外の楽しさを一緒に感じたりすることが大切です。親子の信頼関係が深まると、アドバイスも素直に受け入れやすくなります。
勉強に取り組むときは、ゲームやスマホ、テレビなどを避けて落ち着ける環境を作るのがポイントです。モチベーションを続けるには、目標を決めて計画的に進めることも大切ですが、最初から全部子ども任せにするのは負担が大きいもの。そこで、専属コーチのサポートがある「e-学び」なら、学習計画や進み具合の確認も一緒にできるので安心です。
まずは無料体験から、お子さまに合った学び方を見つけてみませんか?
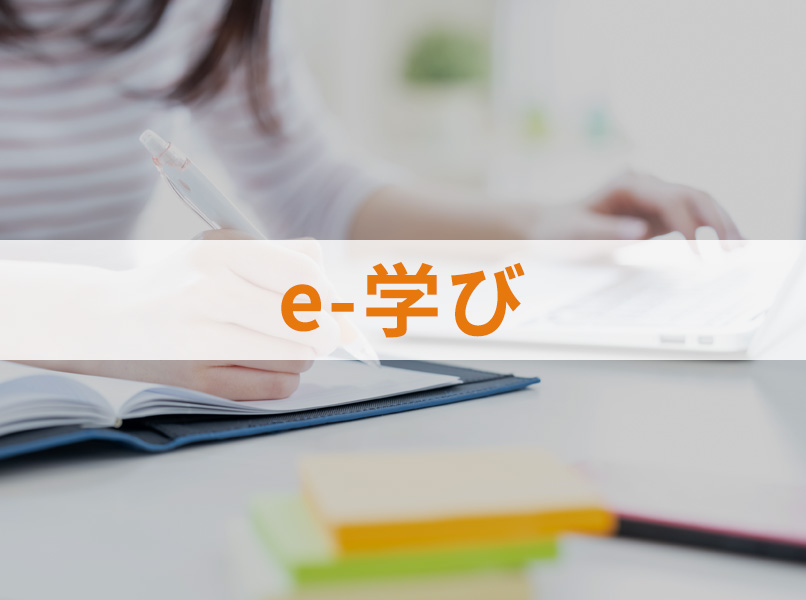
不登校やゲーム依存、学習の遅れに悩むお子さまと保護者の方を支援するオンライン学習サービス「e-学び」の講師。長年、地域の大手学習塾にて個別指導に携わり、様々な背景をもつ生徒と向き合ってきました。不登校やゲーム依存のご相談は随時受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。




