「不登校でゲームしかしない…このままで大丈夫?」と感じている親御さんも少なくありません。不登校の子どもたちがゲームに没頭する理由には、さまざまな心理的背景や状況が隠されています。本記事では、その理由を解説するだけでなく、親としてどう向き合うべきか、具体的な対応策を提案します。
また、親が気を付けるべきNG対応や、ゲームを活かして子どもの成長につなげる方法についても詳しく紹介。子どもに寄り添いながら、未来へのポジティブな道を切り開いていくためのヒントをお伝えします。不登校というデリケートなテーマに対し、現実的かつ具体的なアプローチを知りたい方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
1. 不登校でゲームしかしない…親が抱えるよくある悩みと解決策

現代社会において、不登校の子どもがゲームに没頭する状況は、親にとって深刻な悩みの種となっています。このような問題に直面する親が抱える共通の悩みと、それに対する解決策について掘り下げてみましょう。
「就職できるのか、社会に適応できるのか心配…」
多くの親が、子どもが学校に行かずゲームに時間を費やしている状況に対し、将来に対する強い不安を抱えます。社会に適応する能力や就職の可能性が損なわれるのではないかと心配するのは当然です。しかし、子どもの将来を心配しすぎることで、プレッシャーを与えかねない点にも注意が必要です。親としては、まず子どもが今どのような状況にあるのかをしっかりと把握し、将来への道筋を共に模索していくことが重要です。
「夜中までゲームをして、昼夜逆転してしまった」
昼夜逆転は、不登校の子どもにありがちな問題の一つです。ゲームが生活の中心になると、時間感覚が歪み、健全な生活リズムが崩れてしまいます。ここで重要なのは、ゲームそのものを禁止するのではなく、徐々に生活リズムを整える努力を親子で行うことです。例えば、起床時間や就寝時間を少しずつ調整することで、自然な形で生活のリズムを取り戻すことができます。
「注意すると反発されて暴れるor落ち込む…」
親が子どものゲーム行動に対して注意すると、反発や過剰な感情的反応を引き起こすことがあります。このような場合、対話のタイミングや方法に工夫を加えることが大切です。例えば、冷静な状態で穏やかに話し合う場を設けることで、子どもの心を開かせやすくなります。
「やめさせるべきか、見守るべきか分からない」
ゲームをやめさせるべきなのか、それとも一定の範囲内で見守るべきなのか。これは多くの親が直面する葛藤です。この答えは一概に言えるものではなく、子どもの性格や状況に応じて対応を変える必要があります。重要なのは、子ども自身が自分の行動について考え、向き合える環境を作ることです。
「学校に行かない=勉強しない状態になっている」
不登校の子どもが勉強から遠ざかってしまうことも、親の大きな悩みの一つです。しかし、勉強を強制することで子どもの意欲を奪うリスクがあるため、別の方法で学びを促すアプローチが求められます。たとえば、興味を持てる分野から学びを始めることで、自然に勉強への意欲を引き出すことが可能です。
「親戚や周囲の目が気になって、プレッシャーを感じる」
親戚や近隣の目を気にしてしまい、親自身がプレッシャーを感じるケースも多いでしょう。しかし、他人の目を気にしすぎるあまり、子どもに対して過度の期待を押し付けることは避けるべきです。親としての一番の役割は、子どもが安心して自分を表現できる環境を整えることです。
「フリースクールや塾など合う方法があるのか?」
最後に、子どもに合った支援機関や学習方法を探すことも重要です。フリースクールや家庭教師、オンライン学習など、選択肢はさまざまです。大切なのは、子どもの個性やニーズに合った方法を見つけるために、親子で一緒にリサーチすることです。
2. 子どもがゲームに没頭する本当の5つの理由とは?

理由①「何もしたくない」のではなく、できない事情がある
ゲームに熱中する子どもたちの行動を「怠惰」や「やる気がない」と決めつけるのは誤りです。多くの場合、子どもには学校や日常生活において抱えている困難があり、それを解決する手段を見つけられないため、ゲームに逃げ込んでしまうことがあります。例えば、人間関係のストレスや学業のプレッシャーが原因で、現実世界に向き合うことができない状況が考えられます。子どもが何を「できない」と感じているのかを親が理解し、対話を通じて原因を探ることが解決の第一歩となります。
理由② 現実よりもゲームの方が安心できる
ゲームの世界は、現実とは違い、コントロールが容易であり、失敗があってもすぐにリトライできる特性があります。この特性は、現実社会での失敗や批判を恐れる子どもにとって、非常に安心感を与えるものです。また、ゲームの中では自分のペースで進行できるため、自信を失っている子どもにとって自己肯定感を高める手段ともなります。親はゲームが持つ「安心感」の意味を理解し、子どもが現実でも同様の安心感を感じられる環境作りを模索する必要があります。
理由③ 「ゲームしかない」と思い込んでいる
子どもがゲームに没頭している背景には、「自分にはゲーム以外に居場所がない」との思い込みがある場合があります。たとえば、学校や家庭での居心地が悪いと感じている子どもは、ゲームの中でしか自分の存在価値を見出せなくなることがあります。このような場合、ゲーム以外の活動を少しずつ提案し、他の可能性を示すことで、子どもの視野を広げる努力が必要です。地域のイベントや趣味を見つけるための支援が有効です。
理由④ 親や周囲の期待がプレッシャーになっている
「勉強を頑張れ」「ちゃんとした子になりなさい」という親や周囲の期待が、子どもにとって大きなプレッシャーとなっているケースも少なくありません。このプレッシャーが過剰になると、子どもは現実から逃避する手段としてゲームを選ぶことがあります。親としては、子どもに過度な期待を押し付けるのではなく、子ども自身のペースや考えを尊重しながら見守る姿勢が大切です。
理由⑤ 「今の自分でも認められたい」という思いがある
最後に、子どもたちがゲームに没頭する理由として、現状の自分を受け入れてほしいという願いが挙げられます。ゲームの世界では、努力が明確に結果として反映されるため、達成感や自己承認欲求が満たされやすいのです。この感覚は、現実では得られにくいことも多いため、子どもにとって重要な要素となります。親は子どもが日常生活で成功体験を得られる場を提供し、小さな努力でも認めてあげる姿勢を持つことが必要です。
3. 「ゲームしかしていない状態」から抜け出すには?

ゲームの時間を「禁止」ではなく「管理」する
ゲームを完全に禁止するのは、子どもにストレスを与え、逆効果になることがあります。そこで重要なのは「管理」の視点を持つことです。例えば、一日のゲーム時間を一緒に話し合って設定することで、子ども自身に責任感を持たせることができます。また、ゲームをする前に宿題や家の手伝いを終わらせるというルールを設ければ、生活のバランスを取り戻す一助となるでしょう。このようなアプローチは、子どもが自己管理の能力を身に付けるきっかけにもなります。
ゲームの話題をきっかけに子どもとコミュニケーションをとる
ゲームに熱中している子どもと話をする際に、否定的な態度を取るのではなく、ゲームを通じて子どもの興味や関心を理解する姿勢を持ちましょう。たとえば、「このゲームはどんなところが面白いの?」といった質問をすることで、子どもとのコミュニケーションが活発になります。このような会話を重ねることで、子どもも親に対して心を開きやすくなります。親が子どもの趣味を理解しようとする姿勢は、信頼関係の構築にもつながります。
ゲーム以外の成功体験を積める場を探す
ゲーム以外の活動で成功体験を積むことは、ゲームへの依存を和らげる大きな鍵となります。たとえば、スポーツやアート、プログラミングなど、子どもが興味を持てる分野に挑戦させることで、新たな楽しみを見つけることができます。特に、達成感や自己肯定感を得られる場が重要です。地域のイベントやワークショップに参加させるのもよい方法です。小さな成功を積み重ねることで、子どもは徐々にゲーム以外の活動にも興味を持ち始めるでしょう。
生活リズムを整えるための工夫をする
昼夜逆転の生活習慣を改善することは、不登校の子どもが「ゲームしかしていない状態」から抜け出すために非常に重要です。ただし、無理に早起きを強制するのではなく、少しずつ生活リズムを整えていくことがポイントです。たとえば、朝食を一緒に取る習慣を作る、寝る前にリラックスできる時間を設けるなど、親が積極的にサポートしていくことが求められます。こうした取り組みを通じて、子どもの生活リズムを自然に回復させていくことができます。
子どもの「好き」を活かせる学び方を見つける
最後に、子どもが夢中になれるものを活かし、学びに結びつける方法を考えることも大切です。たとえば、ゲームが好きな子どもには、その延長としてゲームデザインやプログラミングを学ぶ場を提供することが有効です。また、子どもが興味を持つ分野に関連する教材やオンライン講座を探して、一緒に挑戦してみるのも良いでしょう。「好きなこと」が「役に立つこと」に変わる実感を持たせることで、自然と学びへの意欲が高まる可能性があります。
4. 親がやってはいけないNG対応とは?

親が不登校やゲーム依存の子どもと向き合う際、何気なくしてしまう対応が、実は子どもの心に逆効果を与えている場合があります。ここでは、やってはいけないNG対応を具体的に解説し、正しいアプローチを考えます。
「ゲームばかりしていないで勉強しなさい」と頭ごなしに叱る
子どもに勉強を強制し、ゲームを否定する態度は、子どもの自主性を奪い、反発やストレスを生む可能性があります。頭ごなしの叱責は、子どもの自己肯定感を低下させるため、長期的に問題を悪化させる危険性があります。親は、まず子どもの行動の背景や理由を理解し、共感を示した上で、勉強や生活改善への提案をすることが求められます。
「このままじゃ将来ダメになる」と不安をあおる
親が将来への不安を子どもに伝えることで、子ども自身もその不安を強く意識してしまい、逆に動けなくなることがあります。不安を伝えるのではなく、ポジティブな未来像を示し、具体的な行動目標を共に考える姿勢が大切です。
他の子どもと比較して焦らせる
「他の子はもっと頑張っている」といった比較は、子どもにプレッシャーを与えるだけでなく、劣等感を生む可能性があります。他者と比べるのではなく、子ども自身の成長を認め、小さな成功でも褒めることが重要です。子どもは「自分を認めてくれる」親の存在に安心感を覚えます。
いきなりゲームを取り上げてしまう
突然ゲームを取り上げると、子どもは強い抵抗感やストレスを感じる場合があります。これによって親子間の信頼関係が損なわれ、問題がさらに深刻化することもあります。ゲームの時間を徐々に調整したり、代替活動を提案したりすることで、自然にゲームの依存度を減らす方向に進む方法が望ましいでしょう。
親自身が追い詰められてしまう
問題解決に焦りすぎるあまり、親自身が精神的に追い詰められるケースもあります。しかし、親が冷静さを欠くと、子どもとのコミュニケーションにも悪影響が出る可能性があります。親は自分の心の健康にも気を配り、必要であれば専門家や支援機関に相談することを検討してください。
5. まとめ
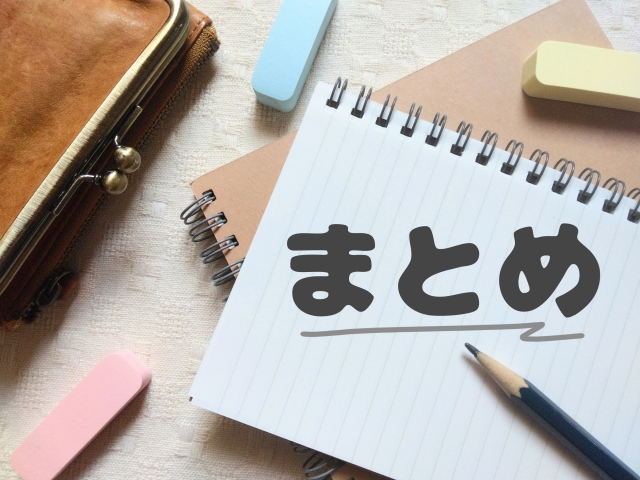
不登校でゲームに没頭する子どもには、安心感を求める心の背景があります。
無理にやめさせるのではなく、気持ちに寄り添い、適切な環境を整えることが大切です。
親の関わり方次第で、ゲームも子どもの成長につながる可能性があります。
▼ 親ができる具体的な行動
✅子どもと冷静に話し合い、ルールを一緒に決める
✅ゲーム以外でも達成感を得られる場を探す
✅生活リズムを整え、ゲーム時間を管理する
もし「ゲーム以外に興味を持てる学び方が見つからない」と感じたら、オンライン学習という選択肢もあります。
「e-学び」では、不登校のお子さま一人ひとりに寄り添った学習サポートを提供しています。
現在無料体験も受付中ですので、気になる方はお気軽にご相談ください。
この機会に、お子さまに合った学習スタイルを見つけてみませんか?
無料体験のお申し込みはこちらからどうぞ!
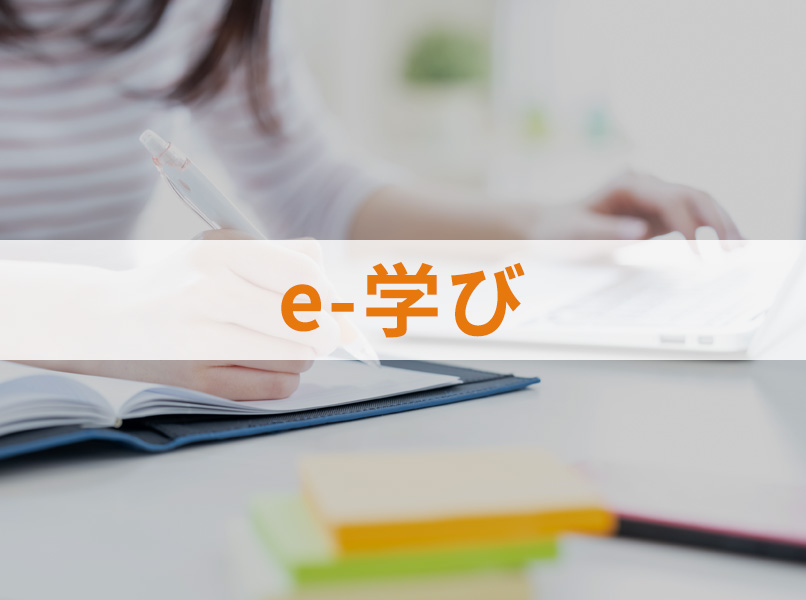
不登校やゲーム依存、学習の遅れに悩むお子さまと保護者の方を支援するオンライン学習サービス「e-学び」の講師。長年、地域の大手学習塾にて個別指導に携わり、様々な背景をもつ生徒と向き合ってきました。不登校やゲーム依存のご相談は随時受け付けています。まずはお気軽にご相談ください。




